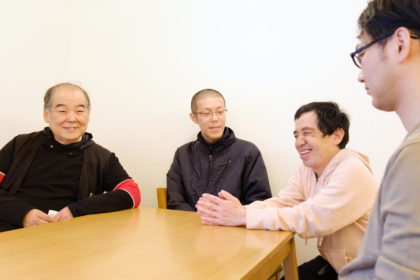「好き・できる・やってみたい」を原動力に、みんなと港まちをつくる|港まちづくり協議会
※この仕事は募集終了いたしました。ご応募どうもありがとうございました。
名古屋港駅のひとつ手前にある、築地口駅。駅に降り立って周辺を散策すると、昔ながらの商店や喫茶店、港まちを思わせるモニュメントなど、味わい深いまちなみが目に入ってきます。
名古屋港に続く大通りに目を向けると、車道を行き交う大きなトラックが何台も。対照的に、横断歩道を渡るおじいちゃんやおばあちゃんは、のんびりとした様子です。



独特の空気が漂う築地口を含む港まちのエリアで、住民・行政とともにまちづくり事業を展開するのが「港まちづくり協議会」(以下、まち協)です。
まち協ではこの春から、新たに一緒に活動する職員を募ることになりました。前回と同様に常勤職員での募集で、経理業務を含む職員業務をひと通り担当してもらう予定とのこと。
となると、経理や簿記の専門知識やスキルが必要?
そもそも、まちづくり事業の業務って具体的にどんなことがあるの?
職員の皆さんは、どんなふうに働いているの?
ハタラクデアイでは過去3回まち協を取材してきましたが、改めて素朴な疑問を聞いてみたくなりました。
お話を伺ったのは大西未来さん、小田ビニシウスさん、西村隆登さん、間宮千晴さん。皆さん、職員としてまちづくりの第一線に立つ方々です。

学生時代にまち協に出会い、アルバイト、非常勤職員、常勤職員を経て2021年度から事務局次長を務める大西さんは、職員の中では在職歴が長く、まち協のこれまでの歩みを深く知る方のひとりです。まずは大西さんに、まち協の活動内容についてお聞きしました。

「まち協では、コンセプトに掲げる『なごやのみ(ん)なとまち』を形にするために、『暮らす、集う、創る』をテーマに年間30以上の事業を展開しています。活動の舞台は、港まち全体です」
事業で扱う内容も非常に多岐にわたります(2023年度の事業事例はこちら)。例えば、港まちに暮らす人たちと関わり合いながら学びの場や集いの機会を提供する事業として、防災を楽しく学んで実践する「みなとまちBOSAI」や、地域住民を中心とした手芸好きが参加する「港まち手芸部」の活動などが継続的に展開されてきました。


一方で、さまざまな切り口から港まちと出会うミニツアー「みなと A GO GO!」や、毎月第2土曜日に開催するマーケットイベント「みなと土曜市」の開催、港のグルメを集めた「港めしBOOK」の制作など、港まちの魅力を発信する事業も充実しています。


多彩な事業を展開するまち協の大きな特徴といえるのが「公金を使ったまちづくりを実践する団体」であること。2006年の競艇場外発売場「ボートピア名古屋」開設に伴い、競艇の施行自治体から「環境整備協力費(「ポートピア名古屋」売上金の1%)」が名古屋市に交付されることになり、まち協はこれを原資として活動をスタートしました。
公金を用いてまちづくりを進める以上、切っても切り離せないのが行政との関わりです。何かアクションする際には、必ず書類の提出が求められます。また、一口に「書類」と言っても種類もさまざまで、作成時には行政の定めるルールに則らなければなりません。職員はそれぞれ、自身が携わる事業に関する書類作成も担っています。
「事業の企画調整やイベントの現場運営などももちろん多いのですが、こういった一般的なPCスキルが求められるような事務的な業務の比重も高めです。中でも、毎月ルーティンで発生するのが、お金周りの業務なんです」
そういって大西さんが取り出したのは、分厚いファイル。月ごとの収入・支払調書がファイリングされています。

支払いに関する書類作成や手配、入力作業がコンスタントに、税理士のチェック依頼などの業務が毎月頭に発生するとのことで、「まとめて進めるのが効率的なのと、お金のことなので、担当職員が一手に引き受けてきました」と大西さんは話します。現在担当している職員の卒業が決まったことから、新たに加わる職員には入職段階からお金周りの業務を任せていこうという考えに至りました。
「経理や簿記に関する専門的な知識やスキルがあると安心かもしれません。でも業務の基本となるフローは整理できていますし、業務で関わる税理士さんや社労士さんも長年お付き合いのある方々なので、未経験でこれから経理業務を学びたい、実践経験を積みたいという人も挑戦しやすいと思います」

ただ、お金周りの業務そのものは、まち協が抱える業務全体の一部。そのため、通常は事業運営にも携わってもらう予定だそうです。
「入職後はまず事業に関わる業務のサポートも経験していただきます。どんな事業がどういった流れで展開されるのか、実践を通して知ることが、まち協の取り組みを理解する一番の近道ですから。担当してもらうお金周りの業務の理解も、より深まると思います」
2024年に入職した間宮さんも「先輩のサポートを通して、仕事内容を少しずつ理解していきました」と振り返ります。もともと、長野県の郷土食「おやき」の魅力を発信するために個人で活動していたという間宮さん。「みなと A GO GO!」参加をきっかけにまち協と出会い、職員となってからは先輩とともに業務経験を積んできました。


「マニュアルもありますし、長年継続している事業も多いので、書類の作成も過去の実績を参考に進められます。実際にやりながら理解するってこともありますが、慣れてくれば大丈夫ですよ」と笑顔を見せる間宮さん。
入職から約1年、メインで担当する業務も増え、21号からリニューアルしたまち協のフリーペーパー「ポットラック新聞 タブロイド判」では、連載記事を持つことになりました。タイトルは「ハプニングおやき」。港まちの人と一緒におやきをつくり、その様子を記事にして掲載しています。紙面には、楽しそうにおやきを作る写真が。目にしたこちらも、思わず口元がほころんでしまいます。

「新しい企画を出し合う中で、おやきの案が採用されて。まさか、大好きなおやきを通してまちの人と関われるようになるとは思ってもみませんでした(笑)」
企画から取材、記事執筆まで経験するのは間宮さんにとって人生で初めての経験で、迷ったり悩んだりすることもしばしば。「そういうときは、すぐに皆さんに相談しています!」と間宮さん。先輩職員からノウハウを学びながら、着実に経験を積んでいるのが伝わってきました。

リニューアルした「ポットラック新聞 タブロイド判」には、「ハプニングおやき」の他にも、さまざまな新しいコーナーが登場しました。「○○さんのある1日」も、その一つ。担当するのは、2023年に入職した西村さんです。

西村さんが担当する事業は、港まちエリア内に作庭した10のコミュニティガーデンの栽培・管理を行う「みなとまちガーデンプロジェクト」や、「港まち俳句の会」など、港まちに暮らす人との関わりが強いものが多めです。


「ここに集まる人は面白い人ばかり。なので、テレビのドキュメンタリー番組のように、まちの人の暮らしを紹介したいと考えました。取材交渉も自分でしていて、『西村くんのお願いなら』と引き受けてくださる方もいて、うれしい限りです」
西村さんは岡崎市の市民団体でもまちづくりの活動に携わっているため、まち協の勤務日は週3日。「時間があればまちに出て、まちの人との関わりを持たないと」との話しぶりに、関係性を築くために、日々限られた時間を有効的に使っている様子がうかがえます。

そんな西村さん、今年の年明けから簿記の勉強に取り組み始めたのだとか。「新しいことに挑戦したいなと思って」と西村さん。毎日忙しそうなのに、大変なのでは…?実務にも、あまり関わりがなさそうですが。
「お金に関する知識って『あったほうが良いもの』だと思うんです。だったら担当の職員さんが卒業するこのタイミングで、簿記を勉強してみようかな、と。新しい職員さんが経理の知識を持っていたら学ばせてもらいたいですし、これから学ぶという人なら、一緒に勉強していきたいですね」

西村さんの言葉に、ハッとしました。仕事はもちろん、毎日の生活にお金は切っても切り離せないもの。知識を身につけることは、無駄にはならないはずです。それなのに「実務に深く関わらないから」と距離を取ってしまうのは、もったいないことなのかもしれません。
「港まちって、本当にたくさんの経験が積めます。経験を通して、職員の個人としての可能性もどんどん広がっていくように思います」と話すのは、4年ほど前から職員として活躍する小田さん。港まちの社交場「NUCO」との出会いをきっかけに、港まちとの関わりを深めてきました。

「僕自身、これまでを振り返ると、想像以上にいろんなことができるようになったと感じます。特に変わったなと感じるのが『伝える力』。まちに暮らす人、訪れる人、行政の方々など、まち協の事業で関わる人は、本当にさまざまです。経験を積むことで、それぞれの人や場面に合った、より伝わりやすい表現や振る舞いといったのを意識できるようになりました。まち協に関わってなかったら、ここまで上手になれなかったと思います」
コミュニティーデザインに関心があり、日頃から港まち以外のコミュニティーにも積極的に顔を出しているという小田さん。最近ではまち協として他の地域のイベントに出店したり、まちづくりに関わる人として講演会に登壇したりと、港まちをより多くの人に知ってもらうためのアクションに携わることも多いのだとか。


また、将来の目標として「外国にルーツを持つ若者のキャリア形成に携わること」を掲げていて、自身の地元・豊田でもコミュニティーデザインを軸に、さまざまな方法で人が集まる場づくりを仕掛けています。個人の活動にも、まち協で培った経験が生きているといいます。
「本当にさまざまな人と出会えて、つながることができたのも、まち協にいたからかな、と。これまでにつながりが生まれた人たちは、僕の将来にも間違いなく関わっていくんだと思います。入職する前と比べたら、僕自身本当に『厚み』が出たなって感じます」

第一線で働く4人の職員の皆さんは、やりたいことや好きなこと、将来の目標もまったく異なります。ですが皆さんそれぞれが、経験してきたことを自分の成長につなげているのではと感じました。
最後に、どんな人ならまち協の職員として活躍できるかを、大西さんに聞いてみました。
「まちづくりって対象がすごく広いので、何かしらの興味関心にヒットしやすいですし、事業を通して興味関心の幅を広げたり、深めたりすることもできます。好奇心と探究心があれば、きっと楽しんでもらえるんじゃないかと思いますね」

大西さんの言葉を受けて、小田さんは「まち協での経験を自分の人生のためのステップとして活用できる人って、きっと強いです」と続けます。
「これまでにも、たくさんの職員がまち協での活躍を経て、今は別の地域やフィールドで活躍しています。やっていることは違っても、みんながそれぞれ、まち協で得た経験をめちゃくちゃ生かしているなと感じます」
大西さん、小田さんの言葉、そして今回の取材を振り返って、ある種の「したたかさ」「貪欲さ」を持つことも、働く上で大事なのでは、と思いました。まち協で得られるたくさんの経験を、自分の成長に生かす、経験したことを無駄にしない。そんな強さを、職員の皆さんは持っていると感じました。
まち協は2025年度に、活動スタートから20年目を迎えます。2025年度は2024年度に引き続き、まち協のビジョンの再構築にも取り組み、まちの人との対話の機会も今まで以上に設けていくとのことです。
これから始まる1年は、節目を前にした「大きな準備期間」。このタイミングでしか経験できないこともたくさんあるのでは、と期待に胸が高まります。

港まちのためになることを念頭に置きながらも、一方で経験することが自分にとってどう生きるか、生かせるかを考える。その両方を意識できる人であればきっと、たくさんの経験から学び、成長できるのではないでしょうか。そして、その成長が港まちをつくる上でも、ぞんぶんに生きてくるのでは、と思えてなりません。

(取材 2025/2/10 伊藤成美)
| 港まちづくり協議会 | |
| 募集職種 | 事務局員 |
| 契約形態 | 有期雇用契約(1年ごとに更新の可能性あり) |
| 給与 | 時給1,300円(最初の6ヶ月は1,250円) |
| 待遇・福利厚生 | 社会保険加入、健康診断、昇給あり ※ただし労働条件による 通勤手当(実費相当) |
| 仕事内容 | 事務局の運営 港まちづくり協議会が実施するまちづくり活動の企画・実施・運営 ・経理業務を中心とした事務業務 ・ガーデン、子育てなどをテーマとしたコミュニティ活動 ・地域のお祭りなどの賑わいイベント ・アート&デザインを活用した各種プロジェクトの企画運営など ・事業にまつわる広報業務 ・各種事業を進める上での資料作成 ・その他、事務局の運営に必要な業務 |
| 勤務地 | 港まちポットラックビル(名古屋市港区名港1−19−23) |
| 勤務時間 | 週5日 月~土のうち5日(勤務時間はシフトで決定 *土曜日は②) 交代制として、次の勤務時間の組み合わせによる ①午前9時00分〜午後6時00分 ②午前10時30分〜午後7時30分 ③午後12時〜午後9時 |
| 休日休暇 | 月8日(シフトで決定)。 入職時期により年次休暇最大20日、夏季休暇最大5日あり |
| 応募資格 | 資格不問 |
| 求める人物像 | ・港まちづくり協議会の活動に興味がある方 ・まちづくり活動に携わっていきたいと考えている方 ・コミュニケーション力があり、チームワークがとれる方 ・PC スキル(Word、Excel、powerpointなど)がある方 ・社会人経験のある方 |
| 募集期間 | 2025年3月12日から4月12日まで |
| 採用予定人数 | 1名 |
| 選考プロセス | 下記「問い合わせ・応募する」ボタンよりエントリー ↓ 1.エントリー ※応募があれば順次選考を行う予定 2.履歴書による1次選考 3.面接による2次選考 4.採用 ※採用時期は4月以降を予定 |
※この仕事は募集終了いたしました。ご応募どうもありがとうございました。