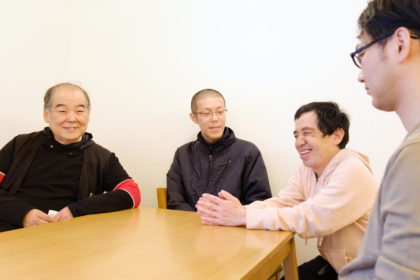第1回 はたらくインタビュー【大ナゴヤ大学・前学長 加藤慎康氏】

はたらく課最初のインタビューは、大ナゴヤ大学(前)学長・加藤慎康(カトウシンヤス)さん。大ナゴヤ大学は、開校から2年間で着々と学生登録数が増えており、現在は2,200人を越えている。その授業・活動内容は幅広く、「愛知県知事候補との“未来の知事さんとカンパーイ”」・「地球の生物部」・「なごやのたからものツアー」など、ネーミングを聞くだけで興味がわいてくる内容ばかり。そんな大ナゴヤ大学の中心にいるのが、加藤学長。普段は、大ナゴヤ大学の活動に注目されることが多いが、今回のインタビューでは、加藤学長自身の“はたらく”にスポットをあてた。
— 学長は普段、どのような仕事をされているのですか?
「一番時間をとっているのが、『大ナゴヤ大学の窓口業務』。メールだけでも、地方自治体や広告代理店から、1日50件くらいの問い合わせが来ます。また、大ナゴヤ大学の代表電話は、自分の携帯電話なので、電話受付も行います。」
——-学長の仕事というと会議やミーティングが多そうなイメージだが、実際は地道な活動が結構な割合を占めている。大ナゴヤ大学には専属のスタッフがおらず、運営メンバーやボランティアスタッフがその一部を支えている体制ということもあり、窓口業務と事務作業が、学長業の60%にものぼるのだ。——-

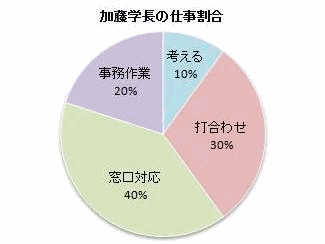
「次に時間をとっているのは『内外の方々との打ち合わせ』。うち半分は、まだ大ナゴヤ大学と接点が無い方々へのアプローチで、過去の活動報告や企画書を持って出向きます。なかなか具体的なアクションに繋がることは少ないですが、なるべく多くの方々と接点を持とうと頑張っています。残りの半分は具体的なプロジェクト(授業、部活動等)の打ち合わせ。プロジェクトが動き出すまでは積極的にかかわりますが、動き出したらメンバーに任せるようにしています。ただ、企業のように、明確な成果を出すことが目的のプロジェクトではない場合が多いので、任せ方はとても難しいですねー。」
——-企業でいうところの、「飛び込み営業」から「企画立案」まで自分一人でやって、具体的に案件が動き出すまで「プロジェクトマネージメント」も自分が担当する、といったイメージみたいだ。うーん、仕事の中身も幅広い!——-
「残りの10%が、大ナゴヤ大学について『考える』時間です。考える内容は、“大ナゴヤ大学では何を大事にすべきか?”、“社会における大ナゴヤ大学の価値は?”など、根幹にかかわることについて。お気に入りの喫茶店に入って、考え込みます。本当は、もっとこの時間をとりたいのですが、事務処理などの日常業務があって、なかなか時間が作れません・・・」
——-一般的な大学・企業の長というと、『考える』仕事が主になってくるのだろう。ただ、大ナゴヤ大学は、立上げから2年と短く、運営面・実務面で加藤学長が関わらないといけない場面が多いみたいだ。——-
— 学長就任前は、大手企業で営業から企画業務まで様々な仕事に携わられていますが、今の「大ナゴヤ大学・学長」という仕事に対する想い・重視していることは?
「今の仕事は好きですね。企業で働いていた時からですが、新しいコト・モノを創り出す時には、すごくワクワクします。大ナゴヤ大学では、常に新しいことが自分の周りで起こっていますし、その変化・化学反応を楽しんでいます。
そして、学長という仕事で重視しているのは、『大ナゴヤ大学に携わるメンバーの気持ち』です。企業の場合は、仕事のプロセスや担当者のモチベーションよりも、最終的な成果が出るかどうかが重要です。一方、大ナゴヤ大学の場合は必ずしも成果を出すことが重要ではなく、活動のプロセスでかかわる人たちがどのような気持ちで取り組めたかを重視しています。大ナゴヤ大学での活動を通じて、参加メンバーが成長し、達成感を得ることが重要で、そのためには参加者に対する『共感のマネージメント』が不可欠であると考えています。実際には、自分が様々な案件・テーマを並行して取り組んでいるため、なかなかできていませんが・・・(苦笑)」
——-一般的な企業の場合、成果を出して収益を得ることが重視されるが、大ナゴヤ大学は「生涯学習」のNPO法人。だからこそ、何か新しいことを企画するにしても、そこで重視する内容も違ってくるのだと感じた。——-


— 加藤学長は、なぜ“学長”という職業を選んだのですか?
「大学を卒業して最初に企業へ入社した時は、『5年で会社を辞めて経営コンサルタントになり、将来的にはビジネスマン向けの学校を開きたい』と考えていました。当時から、ヨットで世界一周した「エリカ号」キャプテン・長江裕明さんの「地球冒険塾」や、「我究館」に代表されるキャリアスクールのように、お互いの考えをぶつけ合う、新しい出会いの場に魅力を感じました。ただ、名古屋にはそのような場がなかったので、自分が名古屋に創るのだという想いが強かったのです。
入社後は、コールセンターの立上げや新商品企画の仕事など、会社の根幹に関わる仕事に携わることができたため、経営コンサルタントへの転職に対する想いは薄くなっていました。そんな会社生活を送って十数年目、体調不良となったのをきっかけに、「自分のやりたいこと」を振り返るようになりました。また、その時期に東レさんが名古屋で研究員を増大させることを知りました。以前、東レ経営研究所主催のMOT研修に参加していることもあって、『東レと連携すれば、注目されている事もあり、MOTの学校が設立できるのでは』と考えました。その後、プログラムディレクターと半年ほど情報交換し、MOTの学校を開講できる可能性を感じ、開校を目指すために会社を辞めることにしました。」
— でも、結局は大ナゴヤ大学の学長に就任したのでは・・・
「会社を辞めてからは、色んな“学びの場”を見に行きました。NPO法人ISL主催のリーダーシップの学校、中国・深圳テクノセンターなどなど。その一環で、シブヤ大学にも生徒として参加したのですが、その発想の斬新さに肝を抜かれ、シブヤ大学にとても惹かれるようになりました。その後、名古屋でもシブヤ大学と同様の団体を設立する流れになり、そのメンバーとして参加したのです。
ただ、学長に就任するかどうかは、1~2ヶ月くらいの間、ものすごく迷いましたね。東レとのMOTの開校計画も中座してしまう可能性も高いし、今までのキャリアをあまり活かすことができないのではないか、とも感じていました。でも、最終的には、『大ナゴヤ大学こそが、自分のやりたかった“学びの場”を創ることではないのか』と想い、学長への就任を決意しました。」
——-大ナゴヤ大学の学長就任までには、様々なことを経験し、考えられていたことを垣間見ることができた。——-


— 大手企業への入社から学長就任まで、様々な決断をしながら進み続けられていますが、なぜ、そんなに大胆かつ積極的に動けるのですか?
「こんなことができるといいんじゃないかと思うと、行動に移しちゃうんです。普通の人は、冷静に考えたりするんだと思いますが、自分はいい意味での『かんちがい野郎』なので、行動できてしまうのだと思います(笑)。
自ら事業を立ち上げる方々には色んなタイプがあると思いますが、自分は関係する方々(先生・スタッフ・生徒さんなど)に対し、なるべくフラットに接するようにしています。ただし、自分が様々な媒体に発信するような時にも、あまり言葉を選ばずに素直な気持ちをさらけ出してしまうので、スタッフから時々注意されたりしますね(苦笑)」
——-言われてみると、加藤学長には、いわゆる「カリスマ的なオーラ」はあまり感じないかも(失礼ながら・・・)。でも、その分、親しみやすさにはあふれていて、それが大ナゴヤ大学の良さである“みんなが気軽に参加できる雰囲気”に繋がっているような気がした。——-
— 大ナゴヤ大学の学長として、今後はどのような活動をしていこうと考えていますか?
「大ナゴヤ大学を通じて、多くの人々に学びの場を提供したいと考えています。そのためには①大ナゴヤ大学らしさのあふれる授業の企画、②企画した授業内容に対する分析・検討、③授業によるスタッフ・参加者の成長の振り返りという3つの軸が必要だと考えています。
現時点では①授業の企画しかできていないのが現状です。もちろん、大ナゴヤ大学らしい授業を創り出すことは大事なのですが、単に『授業を受けて、楽しかった・勉強になった』で終わらせたくないですね。」
——-今後の活動には、加藤学長が就職したときからの最終目的である『学びの場を創ること』に対する、加藤学長のこだわりが感じられた。なるほど、加藤学長は、やっぱり“学長(学ぶ場の長)”なのだ。——-
— 加藤学長にとって、“はたらく”とは?
「今は、「修行の場」ですね。学長という仕事は、今までとは異なる考え方、気持ちの入れ方、スタンスの取り方が求められます。今は経験が少なく、物事が上手く進まないこともありますが、そこでの経験から自ら学び、前を向いて進んで行きたいと思います。」
——-加藤学長へのインタビューの中で多かった発言が、「実際はできてないんですよー」といった反省の弁。最初は、加藤学長の謙虚な性格の現われだと思っていたのだが、「“はたらく”とは修行の場」と聞いて、その反省の弁が、加藤学長の偽らざる本音なんだと実感した。
加藤学長は、大ナゴヤ大学を通じ、多くの人々に学びの場の提供を目指しているが、自身も“学長”という仕事を通じ、多くのことを学び、成長しようとしているのだ。—-—
取材日:2011年6月14日/取材者:小倉永輔