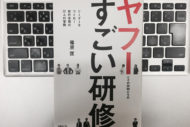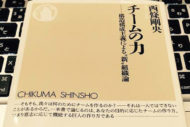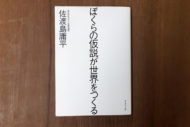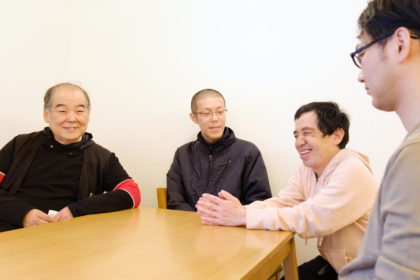誰もが受け入れられ、誰もがふさわしい場所「未来食堂」【はたらく推薦図書 第25回】
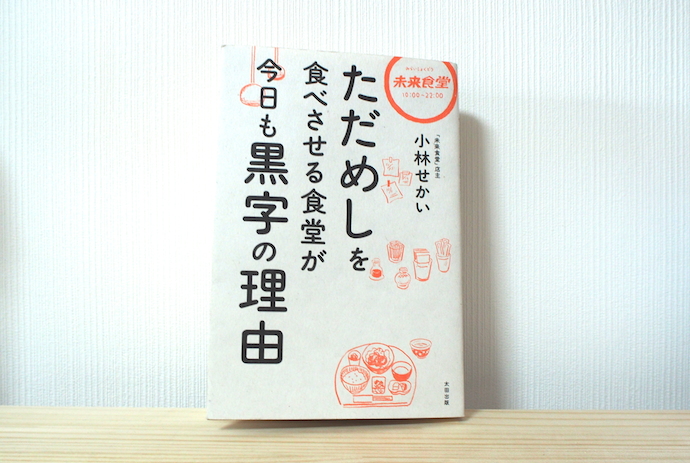
「誰もが受け入れられ、誰もがふさわしい場所」がコンセプトの『未来食堂』。飲食業に”オープンソース”の考え方をとりいれ、事業計画や月次決算などをウェブで公開していることで話題となり、未来食堂の存在を知りました。
お店の運営には、ちょっとしたおかずのリクエストができる「あつらえ」、一度来た人なら誰でも店を手伝える「まかない」など、独自の仕組みがあり、面白そうだなと感じたのと同時に、前著の『未来食堂ができるまで
』(2015年 小学館)も読んでいたので、どのような想いで運営されているのかをもう少し詳しく知りたくなり読み始めました。
思いついたアイデアを実際に形にする方法とは
前半は、「あつらえ」・「まかない」など未来食堂のシステムの話しが中心で、どのような考えでシステムをつくっているのかを知れて面白いのですが、後半に思いついたアイデアを実際に形にする方法について書かれていて、この部分がとても印象に残りました。
アイデアが実現に至るまでの流れは、小林さんの場合、以下のような流れに沿っているそう。経営上の資金計画など絶対に必要不可欠な内容については「定石編」、実現が難しそうなアイデアを落とし込む方法は「独自編」と2つに分けています。
1.息苦しさを見つめ続ける or 情景をものすごく細かく想像する
2.”1枚の絵”がひらめく
3.現実に落としこむ(定石編)(ビジネスモデル)
4.現実に落としこむ(独自編)(独自アイデア)
「1.息苦しさを見つめ続ける」について、世の中の事象を切り分け「×××が問題だから解決しよう」と論理的に問題点を見つけるよりも、自分自身が絶対に嫌だと思うことを掘り下げていくほうが、思いの強い、ブレないものが出来上がっていく。
世間で”良い”と思われる振る舞いをパッチワーク的に縫い合わせただけのアイデアをあまりによく目にする。ワクワクするものを考えたいのであれば、既存の”良い”に振り回されてはいけません。
など、自分自身も誰かが言っている”良い”を、何も考えず”良い”と言っていることはないかと考えさせられました。飲食店を経営している方はもちろん、これから自分で何か事業をはじめたいと思っている方にもお勧めの一冊です。